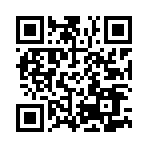2008年12月26日
Natural Action-冬 「僕たちは森にいます」…5
Natural Action-冬
「僕たちは森にいます」…5
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
「僕たちは森にいます」…2
「僕たちは森にいます」…3
「僕たちは森にいます」…4
僕達が森の仕事に関わり、数週間が経ちました。
その動機は、自然環境に少しでも貢献したい、より深く自然と関わりたいという想いからでした。
今日の内容は、僕達が考えているわくわくする計画を皆さんと共有できたらと思います。
このブログを読んでいただいている方にはNatural Actionのベースに足を運んでくださった方も多いかと思います。
来年にはきっと新しいベースで皆様をお出迎えできる事になると思います。
そうなんです。
今、僕達が切り出している木で、ベースを新しく作ってしまおうと考えているんです。
代表のFumiは数年前に、山から木を切り出し、皮むきをして、自分でログハウスを建てました。
作業の一つ一つが本当に楽しかったようです。
きっと色んな夢を抱きながら温かいイメージでゆっくり時間をかけ、気持ちを注いで創ってきたのだと思います。
今では、Emiとかわいい2人の子どもと自分で建てたオーガニックな家で暮らしています。

しかし、今回のログハウス作りはFumiだけではありません。
ガイドの皆も一緒です。



ベースがどんな風に作られていくのかも、
このブログで画像を入れてタイムリーに報告させていただきますね。
さらに、もう一つ計画があるんです。
山で木を運び出すためには作業道が必要になるのですが、
その作業道を利用して、
誰にも気兼ねなく楽しめる最高のマウンテンバイク・ツアーのフリー・ライドパークとして、
美しい健全な森に皆様を案内し、
一緒にマウンテンバイクやその風景を楽しめたらと企画しています。

本当に綺麗な風景なんですよ。
日常生活の中では目にしないような風景があるんです。
立派な木がまっすぐに上高く空に向かって伸び、
適度に間隔が空いた緑の地面には幻想的に光が木洩れています。
森のミストを全身に浴びて、思わず深く息を吸い込みたくなるような空気。
鼻腔を抜ける森の香りと、鳥の声、風に揺られて木々の枝がこすれる音。
深く森と同調してくると、森の命さえも感じられるんです。

今年MTBツアーに参加してくださった皆様、
来シーズンは僕らの手作りのトレイルに是非遊びに来てください!!
シーズン中に皆様の沢山の感動を生み出せるように、
そして、遊びに来てくださる皆様と一緒に過ごさせていただく時間を楽しみにしながら、
心を込めて日々作業を続けていきます。
僕達に出来る事は本当に小さな事ですが、
少しでも、人と森とのつながりを創造していけたらと思っています。
これからは作業の様子や森の仕事を通じて日々感じたことなど記事にしていきます。
今回も最後まで読んでくださって有難うございました。
ご意見やご質問も大歓迎です。
気軽にコメントしてくださいね。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
「僕たちは森にいます」…5
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
「僕たちは森にいます」…2
「僕たちは森にいます」…3
「僕たちは森にいます」…4
僕達が森の仕事に関わり、数週間が経ちました。
その動機は、自然環境に少しでも貢献したい、より深く自然と関わりたいという想いからでした。
今日の内容は、僕達が考えているわくわくする計画を皆さんと共有できたらと思います。
このブログを読んでいただいている方にはNatural Actionのベースに足を運んでくださった方も多いかと思います。
来年にはきっと新しいベースで皆様をお出迎えできる事になると思います。
そうなんです。
今、僕達が切り出している木で、ベースを新しく作ってしまおうと考えているんです。
代表のFumiは数年前に、山から木を切り出し、皮むきをして、自分でログハウスを建てました。
作業の一つ一つが本当に楽しかったようです。
きっと色んな夢を抱きながら温かいイメージでゆっくり時間をかけ、気持ちを注いで創ってきたのだと思います。
今では、Emiとかわいい2人の子どもと自分で建てたオーガニックな家で暮らしています。
しかし、今回のログハウス作りはFumiだけではありません。
ガイドの皆も一緒です。
ベースがどんな風に作られていくのかも、
このブログで画像を入れてタイムリーに報告させていただきますね。
さらに、もう一つ計画があるんです。
山で木を運び出すためには作業道が必要になるのですが、
その作業道を利用して、
誰にも気兼ねなく楽しめる最高のマウンテンバイク・ツアーのフリー・ライドパークとして、
美しい健全な森に皆様を案内し、
一緒にマウンテンバイクやその風景を楽しめたらと企画しています。
本当に綺麗な風景なんですよ。
日常生活の中では目にしないような風景があるんです。
立派な木がまっすぐに上高く空に向かって伸び、
適度に間隔が空いた緑の地面には幻想的に光が木洩れています。
森のミストを全身に浴びて、思わず深く息を吸い込みたくなるような空気。
鼻腔を抜ける森の香りと、鳥の声、風に揺られて木々の枝がこすれる音。
深く森と同調してくると、森の命さえも感じられるんです。
今年MTBツアーに参加してくださった皆様、
来シーズンは僕らの手作りのトレイルに是非遊びに来てください!!
シーズン中に皆様の沢山の感動を生み出せるように、
そして、遊びに来てくださる皆様と一緒に過ごさせていただく時間を楽しみにしながら、
心を込めて日々作業を続けていきます。
僕達に出来る事は本当に小さな事ですが、
少しでも、人と森とのつながりを創造していけたらと思っています。
これからは作業の様子や森の仕事を通じて日々感じたことなど記事にしていきます。
今回も最後まで読んでくださって有難うございました。
ご意見やご質問も大歓迎です。
気軽にコメントしてくださいね。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
タグ :薪ストーブ 静岡 富士 富士宮
2008年12月22日
Natural Action-冬「僕たちは森にいます」…4
Natural Action-冬
「僕たちは森にいます」…4
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
「僕たちは森にいます」…2
「僕たちは森にいます」…3
段々と「僕らが森にいる理由」に近付いてきたと思います。
前回のポイントは
・国土の40%に当たる杉・ヒノキの人工林を健全に保つには人の手による管理が必要
・しかし、森の働き手が経済原理によって減り続けている
ということでした。
今回は、森の荒廃の原因とその背景について話を進めさせていただきます。
さて、前回の最後の問いは
「なぜ人はそんなに手が掛る人工林を作ってきたのでしょう?」でした。
昔々は、薪や備長炭でおなじみの木炭の原料になり、
建築木材に使用しやすい杉ヒノキを裏庭の畑を管理する感覚で、
植え、間伐し、育て、切り、使い、循環させていました。
スギ、ヒノキなどの針葉樹は、植えやすく、
成長が早い上に育つとまっすぐな木材として利用でき、
自然災害も防いでくれるため、盛んに植えられてきたのです。
まさに大規模な「畑」のようなですね。

今、花粉症がエスカレートしていますが、
花粉を吐き出している木は、同時期に大規模に戦後に植えられたものです。
復興に対して建築木材が必要だったのです。
日本の林業の歴史は古いのですが、今、花粉を飛散させている人工林は、
短期的に、緊急的に国を挙げての事業として造られたものです。
一斉に大きくなり、花粉を出す時期が今に重なっているのかもしれません。
もしくは、木々が生命的な危機を感じ、
子孫を残すべく大量の花粉を出しているのかもしれません。
適切に間伐がなされ、循環の中で維持されてきた森には、
若い木や、古い木が混在し、今のような花粉の飛散はなかったのかもしれません。
戦後の一斉植樹は国の政策によって舵取りされてきました。
しかし、高度経済成長を経て、日本の経済力が増し、
日本製品が跳ぶように売れるようになった頃、貿易黒字の問題が発生します。
農業分野においては、国は減反政策で米の生産縮小に乗り出し、
外圧に負け、牛肉・オレンジの輸入を解禁。
残念ながら国内の農業従事者に対する冷たい政策が続いていきます。

経済力の飛躍は、人件費の安い国からの輸入に時代のトレンドが移ります。
つまり、経済の問題です。
そして、国の第一次産業の冷遇の結果とも言い換えられるかもしれません。
一つの数字を紹介します。
国産材の自給率(日本で消費される木材に占める国産材の比率)は
どれくらいだと思いますか?
ちなみに食料のカロリーベースの自給率は39%です。
答えは、20%!!
国内に木があるのに、20%という数字です。
日本の恵まれた国土には、多くの山林資源があります。
問題なのは、山林が豊富にある国なのに、
経済原理のセオリーに沿い、外国から安価な木材を持ってくる事なのです。
経済の問題で自然環境を蔑ろにしてきた時代は、もう長くは続かないと思っています。
経済の問題で、森を維持、つまり環境の維持を担う働き手が姿を消そうとしています。
人工林の手入れである間伐を促すため、森に働き手を呼び戻すために、
それが少々割高であろうと、地産地消にこだわり国産材に目を向けて欲しいと思います。
戦後植えられた木が一斉に間伐が必要な時期に来ているのに、
森での働き手がいない。
戦後国の政策として、先人の多大な労力、莫大な資金の投資が無駄になってしまうのです。
森が荒れ果ててしまうのです。
戦後、車や重機が無い時代に、
自分の足だけで山の急斜面を何度も何度も登り、下り、
手道具だけで森を作ってきた人たちの汗と労力に敬意をはらい、
無駄にしたくないという気持ちや、
放置されている木も、そんな先人の想いも非常にもったいないと、
僕達は考えています。
木に目を向けて見ましょう。
違う角度から環境問題を見ることが出来るかもしれません。
もう一度。
健全な森は、水も浄化します。
健全な森は、生命を育みます。
健全な森が、僕達の精神情緒に与えてくれている恩恵を思い出してください。
僕達の生まれた、この日本の森を、脈々と受け継がれてきた文化を
誰かが継承し伝えていかなければと思います。
そんな想いから、僕たちNatural Actionの素人集団は山に入る事になったわけです。
自分たちの手で少しでも環境に貢献する。
僕たちが間伐した森でゆっくりと濾過されたきれいな水は、
稲瀬川となり、ラフティングのフィールドとなる富士川に注ぎ入ります。

そして駿河湾で待っている魚や海草たちにも栄養を届けます。
この土地の水や森がいつまでもきれいであってほしいと願いつつ、
冬の間は、慣れない森の仕事ですが楽しみながら取り組んでいこうと思います。
次回は、僕達のひそかな計画をお伝えします。
長くなりましたが、今日も最後まで読んでくださり、有難うございました。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
「僕たちは森にいます」…4
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
「僕たちは森にいます」…2
「僕たちは森にいます」…3
段々と「僕らが森にいる理由」に近付いてきたと思います。
前回のポイントは
・国土の40%に当たる杉・ヒノキの人工林を健全に保つには人の手による管理が必要
・しかし、森の働き手が経済原理によって減り続けている
ということでした。
今回は、森の荒廃の原因とその背景について話を進めさせていただきます。
さて、前回の最後の問いは
「なぜ人はそんなに手が掛る人工林を作ってきたのでしょう?」でした。
昔々は、薪や備長炭でおなじみの木炭の原料になり、
建築木材に使用しやすい杉ヒノキを裏庭の畑を管理する感覚で、
植え、間伐し、育て、切り、使い、循環させていました。
スギ、ヒノキなどの針葉樹は、植えやすく、
成長が早い上に育つとまっすぐな木材として利用でき、
自然災害も防いでくれるため、盛んに植えられてきたのです。
まさに大規模な「畑」のようなですね。
今、花粉症がエスカレートしていますが、
花粉を吐き出している木は、同時期に大規模に戦後に植えられたものです。
復興に対して建築木材が必要だったのです。
日本の林業の歴史は古いのですが、今、花粉を飛散させている人工林は、
短期的に、緊急的に国を挙げての事業として造られたものです。
一斉に大きくなり、花粉を出す時期が今に重なっているのかもしれません。
もしくは、木々が生命的な危機を感じ、
子孫を残すべく大量の花粉を出しているのかもしれません。
適切に間伐がなされ、循環の中で維持されてきた森には、
若い木や、古い木が混在し、今のような花粉の飛散はなかったのかもしれません。
戦後の一斉植樹は国の政策によって舵取りされてきました。
しかし、高度経済成長を経て、日本の経済力が増し、
日本製品が跳ぶように売れるようになった頃、貿易黒字の問題が発生します。
農業分野においては、国は減反政策で米の生産縮小に乗り出し、
外圧に負け、牛肉・オレンジの輸入を解禁。
残念ながら国内の農業従事者に対する冷たい政策が続いていきます。

経済力の飛躍は、人件費の安い国からの輸入に時代のトレンドが移ります。
つまり、経済の問題です。
そして、国の第一次産業の冷遇の結果とも言い換えられるかもしれません。
一つの数字を紹介します。
国産材の自給率(日本で消費される木材に占める国産材の比率)は
どれくらいだと思いますか?
ちなみに食料のカロリーベースの自給率は39%です。
答えは、20%!!
国内に木があるのに、20%という数字です。
日本の恵まれた国土には、多くの山林資源があります。
問題なのは、山林が豊富にある国なのに、
経済原理のセオリーに沿い、外国から安価な木材を持ってくる事なのです。
経済の問題で自然環境を蔑ろにしてきた時代は、もう長くは続かないと思っています。
経済の問題で、森を維持、つまり環境の維持を担う働き手が姿を消そうとしています。
人工林の手入れである間伐を促すため、森に働き手を呼び戻すために、
それが少々割高であろうと、地産地消にこだわり国産材に目を向けて欲しいと思います。
戦後植えられた木が一斉に間伐が必要な時期に来ているのに、
森での働き手がいない。
戦後国の政策として、先人の多大な労力、莫大な資金の投資が無駄になってしまうのです。
森が荒れ果ててしまうのです。
戦後、車や重機が無い時代に、
自分の足だけで山の急斜面を何度も何度も登り、下り、
手道具だけで森を作ってきた人たちの汗と労力に敬意をはらい、
無駄にしたくないという気持ちや、
放置されている木も、そんな先人の想いも非常にもったいないと、
僕達は考えています。
木に目を向けて見ましょう。
違う角度から環境問題を見ることが出来るかもしれません。
もう一度。
健全な森は、水も浄化します。
健全な森は、生命を育みます。
健全な森が、僕達の精神情緒に与えてくれている恩恵を思い出してください。
僕達の生まれた、この日本の森を、脈々と受け継がれてきた文化を
誰かが継承し伝えていかなければと思います。
そんな想いから、僕たちNatural Actionの素人集団は山に入る事になったわけです。
自分たちの手で少しでも環境に貢献する。
僕たちが間伐した森でゆっくりと濾過されたきれいな水は、
稲瀬川となり、ラフティングのフィールドとなる富士川に注ぎ入ります。

そして駿河湾で待っている魚や海草たちにも栄養を届けます。
この土地の水や森がいつまでもきれいであってほしいと願いつつ、
冬の間は、慣れない森の仕事ですが楽しみながら取り組んでいこうと思います。
次回は、僕達のひそかな計画をお伝えします。
長くなりましたが、今日も最後まで読んでくださり、有難うございました。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
タグ :薪ストーブ 静岡 富士 富士宮
2008年12月19日
Natural Action-冬「僕たちは森にいます」…3
Natural Action-冬
「僕たちは森にいます」…3
前シリーズはこちらから
↓
「僕達は森にいます」…1
「僕達は森にいます」…2
では、続きの森の現状です。
前回お話した健全な森の果たす機能と、
健全な森の作り方についてお話しさせていただきます。
森の機能は
1、生命を養う
2、酸素を作り大気を浄化する
3、水を蓄え、少しずつ放出する
4、土を作る
でした。
健全な森を保つために、「木を切るな!!」でしょうか?
そんな事はないのです。
森林はその成長量の範囲内で伐採するならば消滅する事はありません。
また、消費量以上に植林するなど、保全し修復するなら問題はありません。
そして、「自然林」と「人工林」には健全な森の作り方に違いがあります。
大雑把に言うと
「自然林」は放っておけば、寿命を終えた老木は自然に枯れ、その隙間から新しい木々が生えてきます。
自然淘汰のなかで生態系を自分で維持できる森です。
一方「人工林」はというと?
ここがポイント!!
「人工林」覚えていますか?
人が植えた杉とヒノキの森です。
「人工林」は常に人の管理が必要です。

管理とは?
・木の枝を払う事
枝が生い茂ると日光が地面に届かず、下草が生えません。
下草が生える事で、草が土を掴み土砂崩れを防ぎます。
また、新しく生えようとする背の低い植物は永遠に日の光にさらされることがなく
育たず、背の高い木の独占状態となり、同年代に植えた木のみが生える、
木の年齢に多様性が生まれません。
・間伐をする事
一定の面積に密生している木の本数を減らす事により、
木々は深く広く根を張る事ができ、土壌を固定し、
根から沢山の水を取り入れることで光合成も活発に行い、強い木が育ちます。
また、強く太く、枝の手入れをされている木は使用用途も市場での価値も増えます。
最初は高密度に苗木を植えて競争させ、成長に応じて間伐を繰り返して、
良質な木材を生産するというのは、日本古来の受け継がれた技術です。
間伐がなされない山は、いわゆる放置林といわれ、自然災害や病虫害に弱く、
ひ弱にモヤシのように根の張れない細い木は風や雪によって折れ、
土壌を固定する能力もなく、土壌は痩せ、土砂崩れを起こし、保水力も期待できません。
暗く、生命力のない森になります。
材木としての用途もなく、市場に出ても値が付きません。
さらに、市場に出すまでのコストに見合わないので、
結局、山林家としては放置せざるを得ないのです。
つまり健全な森の機能を果たす事の出来ない状態です。

このように人工林を健全な状態に保つのには人の手が必要なのです。
杉・ヒノキの「人工林」は、日本の森全体の4割です。
これは、イコール、手入れが必要な森の割合です。
一昔前までは、間伐・枝打ちと言った作業がなされ、
健全な森から出荷される間伐材には用途があり、値も付き、採算に合うため
人が山で生計を立てていく事が可能でした。
地産地消で、外国の森林破壊の原因も作らず、
国産の木が国内で循環する望ましい情況です。
しかし現状は違います。
第一次産業に分類される農林水産、いずれの産業からも労働者は離れていきます。
生計が成り立たないのです。
こと林業を考える際には、
労働力が安い外国材に価格で競争は出来ないのです。
安価な外材が市場を席巻している為に、
日本の国産材は売れません。
売れなければ商売にならないので、林業を生業としてきた人たちが山から姿を消します。
自然環境の大本である山を管理する大事な人たちです。
姿を消されては困る人たちです。
さらに、この点を考えてください。
日本の山は急傾斜地が多く、森に生えている木を林道に出すまで、
そして、そこから市場まで持っていく事に労力がかかるのです。
例えば、アラスカやシベリア、東南アジアは比較的平らな大地に森が形成されているので、
大型のショベルカー、大型トラックが容易に入り、
市場に出すまでのコストは比較にならないくらい安いのです。
これらの国では木を切ったら自然には生えてこず、
植樹をしても育ちにくいという地理的特性があります。
人件費だけでなく、地理的な要因も、国産材が高い事の大きな理由です。
さらに、外国からの木材の輸入には上記の他にも大きな問題点があります。
その一つは、ウッドマイレージの問題。
フードマイレージと同様に、日本の消費者の手に届くまでに、輸送のために多くの重油を必要とすることです。
そして、二つ目の問題。
木材輸出国、例えば、アラスカ、東南アジア、ブラジルをイメージしてみましょうか。
彼らの生活には森が必要不可欠だったはずです。
森に集まる動物や薬草、木の実、もちろん木、森への信仰、
そして、健全な森が果たす保水や空気の浄化などの人が生きていくために不可欠な機能。
日本の側から見たら安いからと言う理由で、
輸出国である主に発展途上国の人々の生活の糧をお金と引き換えに奪ってしまっている側面もあるのです。

個人的には食の問題と同様、
木材に関しても、地産地消のトレンドに移行していくだろうと思っています。
地産地消が、環境問題や富の偏在などの大きな大きな問題を小さくしていく一つの方法論なのかもしれません。
それでは、なぜ人はそんなに手が掛る人工林を作ってきたのでしょう?
管理がいらなくても健全な森の機能を果たせる「自然林」の方が良いような気がしませんか?
長くなってしまったので、次記事に譲ります。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
「僕たちは森にいます」…3
前シリーズはこちらから
↓
「僕達は森にいます」…1
「僕達は森にいます」…2
では、続きの森の現状です。
前回お話した健全な森の果たす機能と、
健全な森の作り方についてお話しさせていただきます。
森の機能は
1、生命を養う
2、酸素を作り大気を浄化する
3、水を蓄え、少しずつ放出する
4、土を作る
でした。
健全な森を保つために、「木を切るな!!」でしょうか?
そんな事はないのです。
森林はその成長量の範囲内で伐採するならば消滅する事はありません。
また、消費量以上に植林するなど、保全し修復するなら問題はありません。
そして、「自然林」と「人工林」には健全な森の作り方に違いがあります。
大雑把に言うと
「自然林」は放っておけば、寿命を終えた老木は自然に枯れ、その隙間から新しい木々が生えてきます。
自然淘汰のなかで生態系を自分で維持できる森です。
一方「人工林」はというと?
ここがポイント!!
「人工林」覚えていますか?
人が植えた杉とヒノキの森です。
「人工林」は常に人の管理が必要です。

管理とは?
・木の枝を払う事
枝が生い茂ると日光が地面に届かず、下草が生えません。
下草が生える事で、草が土を掴み土砂崩れを防ぎます。
また、新しく生えようとする背の低い植物は永遠に日の光にさらされることがなく
育たず、背の高い木の独占状態となり、同年代に植えた木のみが生える、
木の年齢に多様性が生まれません。
・間伐をする事
一定の面積に密生している木の本数を減らす事により、
木々は深く広く根を張る事ができ、土壌を固定し、
根から沢山の水を取り入れることで光合成も活発に行い、強い木が育ちます。
また、強く太く、枝の手入れをされている木は使用用途も市場での価値も増えます。
最初は高密度に苗木を植えて競争させ、成長に応じて間伐を繰り返して、
良質な木材を生産するというのは、日本古来の受け継がれた技術です。
間伐がなされない山は、いわゆる放置林といわれ、自然災害や病虫害に弱く、
ひ弱にモヤシのように根の張れない細い木は風や雪によって折れ、
土壌を固定する能力もなく、土壌は痩せ、土砂崩れを起こし、保水力も期待できません。
暗く、生命力のない森になります。
材木としての用途もなく、市場に出ても値が付きません。
さらに、市場に出すまでのコストに見合わないので、
結局、山林家としては放置せざるを得ないのです。
つまり健全な森の機能を果たす事の出来ない状態です。

このように人工林を健全な状態に保つのには人の手が必要なのです。
杉・ヒノキの「人工林」は、日本の森全体の4割です。
これは、イコール、手入れが必要な森の割合です。
一昔前までは、間伐・枝打ちと言った作業がなされ、
健全な森から出荷される間伐材には用途があり、値も付き、採算に合うため
人が山で生計を立てていく事が可能でした。
地産地消で、外国の森林破壊の原因も作らず、
国産の木が国内で循環する望ましい情況です。
しかし現状は違います。
第一次産業に分類される農林水産、いずれの産業からも労働者は離れていきます。
生計が成り立たないのです。
こと林業を考える際には、
労働力が安い外国材に価格で競争は出来ないのです。
安価な外材が市場を席巻している為に、
日本の国産材は売れません。
売れなければ商売にならないので、林業を生業としてきた人たちが山から姿を消します。
自然環境の大本である山を管理する大事な人たちです。
姿を消されては困る人たちです。
さらに、この点を考えてください。
日本の山は急傾斜地が多く、森に生えている木を林道に出すまで、
そして、そこから市場まで持っていく事に労力がかかるのです。
例えば、アラスカやシベリア、東南アジアは比較的平らな大地に森が形成されているので、
大型のショベルカー、大型トラックが容易に入り、
市場に出すまでのコストは比較にならないくらい安いのです。
これらの国では木を切ったら自然には生えてこず、
植樹をしても育ちにくいという地理的特性があります。
人件費だけでなく、地理的な要因も、国産材が高い事の大きな理由です。
さらに、外国からの木材の輸入には上記の他にも大きな問題点があります。
その一つは、ウッドマイレージの問題。
フードマイレージと同様に、日本の消費者の手に届くまでに、輸送のために多くの重油を必要とすることです。
そして、二つ目の問題。
木材輸出国、例えば、アラスカ、東南アジア、ブラジルをイメージしてみましょうか。
彼らの生活には森が必要不可欠だったはずです。
森に集まる動物や薬草、木の実、もちろん木、森への信仰、
そして、健全な森が果たす保水や空気の浄化などの人が生きていくために不可欠な機能。
日本の側から見たら安いからと言う理由で、
輸出国である主に発展途上国の人々の生活の糧をお金と引き換えに奪ってしまっている側面もあるのです。

個人的には食の問題と同様、
木材に関しても、地産地消のトレンドに移行していくだろうと思っています。
地産地消が、環境問題や富の偏在などの大きな大きな問題を小さくしていく一つの方法論なのかもしれません。
それでは、なぜ人はそんなに手が掛る人工林を作ってきたのでしょう?
管理がいらなくても健全な森の機能を果たせる「自然林」の方が良いような気がしませんか?
長くなってしまったので、次記事に譲ります。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
2008年12月16日
Natural Action-冬 「僕たちは森にいます」…2
Natural Action-冬
「僕たちは森にいます」…2
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
前回、の最後に
・なぜ僕たちが森にいるのか?
・なぜ日本の森が健全な状態にないか?
と書きました。
今回でその答えをお伝え出来そうにないので、順を追って
「日本の森の現状」をお伝えします。
少々長い話になりますので気長に読んでいただければと思います。
日本の国土の約7割が山岳地帯とされています(緑被率66%)。
フィンランドの緑被率70%についで世界第二位の森林国です。
こんなに豊かな森林資源を持つ日本ですが、
有り余っているはずなのですが、実は
木材消費の8割を外国から輸入しています。
国内の人件費が高いために途上国の安い木材を輸入し、
これによって、途上国森林破壊が進んでいます。
さらに安いから大量に使い捨てをしてしまうと言う経済構造が働いています。
最近ファミリーマートに行かれた方いらっしゃいますか?
レジ横に、国産材を使った割り箸が5円で売られていませんでしたか?
今までタダで貰えていた割り箸が有料に、しかも国産材?
なぜでしょう?
その問いに答えるためにも、少し、日本の森林についてお話します。
山、つまり木が生えている山林には2種類あります。
一つは「自然林」。
多種多様な木々が生い茂る自然のそのものの森です。
葉っぱが大きく、くねくねした枝を横に広げる広葉樹が多いのが特色です。

もう一つは「人工林」。
建築木材や箸を含む木工品、昔だったら火力の原料を用途として、
人が苗木を植えて作り維持してきた森です。
人工林は日本の山林全体の4割と言われています。
生えている木の構成としては、
杉・ヒノキに代表される葉っぱが細く、幹はまっすぐに伸びている木々です。

では、「自然林」と「人工林」両者の性質の違いを見ていきましょう。
「自然林」は、沢山の種類の木があります。
他方、「人工林」は、人が植えた杉やヒノキの単一の木です。
「自然林」は木々の多様性に呼応し、そこに住む虫や鳥や動物も多様です。
一方、杉・ヒノキの「人工林」には生物の多様性にはそれほど富んでいません。
両方の森の中で動物の鳴き声の量に違いがあります。
もちろん杉・ヒノキが好きな動植物もいます。
「自然林」は葉っぱが大きい広葉樹で構成されているので木に水を蓄え、酸素を作る力が多いとされています。
杉・ヒノキの「人工林」は葉っぱが細い針葉樹なので酸素を作る力が少ないとされています。
では、両者の違いを念頭に、
次は、森の持つ機能について代表的なものを4つ紹介します。
1、生物を養う
木の実が生物を養い、その生物はまた別の生物を養い、
生命を支えあい、生態系が成り立ち、多くの生命の生息の地となり、
生態系を保全する働きがある。
2、酸素を作り、大気を浄化する
二酸化炭素を吸収し、酸素を作り出す。
3、水を蓄え、少しずつ放出する
もし、森林がなければ、降った雨水は土石と共に一度に流れ出し、
逆に降らないときには干上がってしまいます。一度降った雨を蓄え、
少しずつ水を放流する事は、上記のように結構大切な事です。
そして、木々の葉から出される水蒸気が上空に昇り水の粒が出来、
それが集まって雲の構成を助けます。雨を降らせるのも森の働きです。
4、土を作る
森に生きる虫や鳥や動物のフンや死骸に葉っぱが落ちて、
その上にまたフンがたまり有機物を豊富に含む土を作ります。
こうして出来た土は少しずつ川下に流され、川底や平野にたまります。
平野にある豊かな土は森から流れてきたものですが、
鉄砲水の時のように森の保水力がない場合、
また川の護岸工事でコンクリートで固めてしまうと、土は平野にたまらず、
海に直行し平野の地味は痩せ、農作物も育たなくなります。
つまり、この4つの森の機能が十分に発揮されている状態が「健全な森」と呼べるわけです。
そして、「人工林」と「自然林」では健全な森の作り方が変わってきます。
ちょっと話が長くなってしまいそうです。
読んでいただくのにも疲れそうなので、連載にします。
次回も日本の森林の現状についてお話を進めます。
すぐにアップしますので、少々お待ちください。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
「僕たちは森にいます」…2
前シリーズはこちらから
↓
「僕たちは森にいます」…1
前回、の最後に
・なぜ僕たちが森にいるのか?
・なぜ日本の森が健全な状態にないか?
と書きました。
今回でその答えをお伝え出来そうにないので、順を追って
「日本の森の現状」をお伝えします。
少々長い話になりますので気長に読んでいただければと思います。
日本の国土の約7割が山岳地帯とされています(緑被率66%)。
フィンランドの緑被率70%についで世界第二位の森林国です。
こんなに豊かな森林資源を持つ日本ですが、
有り余っているはずなのですが、実は
木材消費の8割を外国から輸入しています。
国内の人件費が高いために途上国の安い木材を輸入し、
これによって、途上国森林破壊が進んでいます。
さらに安いから大量に使い捨てをしてしまうと言う経済構造が働いています。
最近ファミリーマートに行かれた方いらっしゃいますか?
レジ横に、国産材を使った割り箸が5円で売られていませんでしたか?
今までタダで貰えていた割り箸が有料に、しかも国産材?
なぜでしょう?
その問いに答えるためにも、少し、日本の森林についてお話します。
山、つまり木が生えている山林には2種類あります。
一つは「自然林」。
多種多様な木々が生い茂る自然のそのものの森です。
葉っぱが大きく、くねくねした枝を横に広げる広葉樹が多いのが特色です。

もう一つは「人工林」。
建築木材や箸を含む木工品、昔だったら火力の原料を用途として、
人が苗木を植えて作り維持してきた森です。
人工林は日本の山林全体の4割と言われています。
生えている木の構成としては、
杉・ヒノキに代表される葉っぱが細く、幹はまっすぐに伸びている木々です。

では、「自然林」と「人工林」両者の性質の違いを見ていきましょう。
「自然林」は、沢山の種類の木があります。
他方、「人工林」は、人が植えた杉やヒノキの単一の木です。
「自然林」は木々の多様性に呼応し、そこに住む虫や鳥や動物も多様です。
一方、杉・ヒノキの「人工林」には生物の多様性にはそれほど富んでいません。
両方の森の中で動物の鳴き声の量に違いがあります。
もちろん杉・ヒノキが好きな動植物もいます。
「自然林」は葉っぱが大きい広葉樹で構成されているので木に水を蓄え、酸素を作る力が多いとされています。
杉・ヒノキの「人工林」は葉っぱが細い針葉樹なので酸素を作る力が少ないとされています。
では、両者の違いを念頭に、
次は、森の持つ機能について代表的なものを4つ紹介します。
1、生物を養う
木の実が生物を養い、その生物はまた別の生物を養い、
生命を支えあい、生態系が成り立ち、多くの生命の生息の地となり、
生態系を保全する働きがある。
2、酸素を作り、大気を浄化する
二酸化炭素を吸収し、酸素を作り出す。
3、水を蓄え、少しずつ放出する
もし、森林がなければ、降った雨水は土石と共に一度に流れ出し、
逆に降らないときには干上がってしまいます。一度降った雨を蓄え、
少しずつ水を放流する事は、上記のように結構大切な事です。
そして、木々の葉から出される水蒸気が上空に昇り水の粒が出来、
それが集まって雲の構成を助けます。雨を降らせるのも森の働きです。
4、土を作る
森に生きる虫や鳥や動物のフンや死骸に葉っぱが落ちて、
その上にまたフンがたまり有機物を豊富に含む土を作ります。
こうして出来た土は少しずつ川下に流され、川底や平野にたまります。
平野にある豊かな土は森から流れてきたものですが、
鉄砲水の時のように森の保水力がない場合、
また川の護岸工事でコンクリートで固めてしまうと、土は平野にたまらず、
海に直行し平野の地味は痩せ、農作物も育たなくなります。
つまり、この4つの森の機能が十分に発揮されている状態が「健全な森」と呼べるわけです。
そして、「人工林」と「自然林」では健全な森の作り方が変わってきます。
ちょっと話が長くなってしまいそうです。
読んでいただくのにも疲れそうなので、連載にします。
次回も日本の森林の現状についてお話を進めます。
すぐにアップしますので、少々お待ちください。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
2008年12月12日
Natural Action-冬 「僕たちは森にいます」…1
Natural Action-冬
「僕たちは森にいます」…1
4月から11月までの間、僕たちは太陽の下、
富士川や富士山麓をフィールドとして遊ばせてもらいました。
もともと自然の中で遊ばせて貰うこと、
自然の中に身を置くことが大好きな僕たちにとって、
何が一番うれしいだろうって考えました。
なんだと思いますか? とてもシンプルだけどガイドの共通の答え。
それは、
「水がきれいなこと」

ラフティングで川を下っていても、たまに海に行ってサーフィンをしている時も、
常に感じる事は、こんなにシンプルなことでした。
逆に、水が汚い時に覚える寂しく、残念な気持ち。
毎年一回、クリーンリバーラフティングを企画し、
普段遊ばせて頂いている川のゴミを拾う時にも、
ゴミの量に悲しい気持ちになり、
少しでもきれいにする事で、すがすがしい気持ちになります。
「水がきれい」。
本当に大切なことです。
では、どうしたら水はきれいになるのでしょうか?
循環する水の一生を考えてみましょう。
雨が、山々に降り注ぎます。
降り注いだ雨は、木々や植物を潤わせながら、川となり、湖となり、地下水となり、最後は役目を終えて海に還って行きます。
そして、その大いなる海は太陽の熱で暖められて、役目を終えた水の精を運び、雲となって形を変え、又、水をもたらしてくれます。
水の一生が、地球が存続している限り繰り返される恵まれた国土に僕たちは住んでいます。
そして、その水は多くの穀物を生み出し、野菜を生み出し、米を生み出し、野に花々を咲かせ、
四季折々移り行く中で、飲料水、工業用水とさまざまな恵みを与えてくれるのです。
巡り、循環する水がどこで浄化され、ミネラルを得るかといえば、
それは、やはり森なのです。

健全な森は水を浄化します。
健全な森は生命を育みます。
健全な森から始まる水の大いなる循環から僕たちは様々な恩恵を受けます。
こんな話を聞いた事がありますか?
広島のカキの養殖をしている漁師さんが森の手入れを始めた話。
漁獲量が減ったり、カキが大きく育たない原因が海水にミネラルやリンを含む栄養素が減少したからだと考え、元をたどっていくと、森に行き着いた。
そして、長い年月をかけて人工林を整備し、植樹をした。
その結果、いままで以上に立派なカキが育つようになった。
そうなんです。
森をきれいにする事が、僕たちがいつもお世話になっている川の水をきれいにする事にする事にダイレクトに繋がるのです。

しかし、今、日本の森は健全な状態にはありません。
なぜでしょうか?
そして、Natural Actionスタッフが森にいる訳も。
次回に記事にしますね。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================
「僕たちは森にいます」…1
4月から11月までの間、僕たちは太陽の下、
富士川や富士山麓をフィールドとして遊ばせてもらいました。
もともと自然の中で遊ばせて貰うこと、
自然の中に身を置くことが大好きな僕たちにとって、
何が一番うれしいだろうって考えました。
なんだと思いますか? とてもシンプルだけどガイドの共通の答え。
それは、
「水がきれいなこと」

ラフティングで川を下っていても、たまに海に行ってサーフィンをしている時も、
常に感じる事は、こんなにシンプルなことでした。
逆に、水が汚い時に覚える寂しく、残念な気持ち。
毎年一回、クリーンリバーラフティングを企画し、
普段遊ばせて頂いている川のゴミを拾う時にも、
ゴミの量に悲しい気持ちになり、
少しでもきれいにする事で、すがすがしい気持ちになります。
「水がきれい」。
本当に大切なことです。
では、どうしたら水はきれいになるのでしょうか?
循環する水の一生を考えてみましょう。
雨が、山々に降り注ぎます。
降り注いだ雨は、木々や植物を潤わせながら、川となり、湖となり、地下水となり、最後は役目を終えて海に還って行きます。
そして、その大いなる海は太陽の熱で暖められて、役目を終えた水の精を運び、雲となって形を変え、又、水をもたらしてくれます。
水の一生が、地球が存続している限り繰り返される恵まれた国土に僕たちは住んでいます。
そして、その水は多くの穀物を生み出し、野菜を生み出し、米を生み出し、野に花々を咲かせ、
四季折々移り行く中で、飲料水、工業用水とさまざまな恵みを与えてくれるのです。
巡り、循環する水がどこで浄化され、ミネラルを得るかといえば、
それは、やはり森なのです。

健全な森は水を浄化します。
健全な森は生命を育みます。
健全な森から始まる水の大いなる循環から僕たちは様々な恩恵を受けます。
こんな話を聞いた事がありますか?
広島のカキの養殖をしている漁師さんが森の手入れを始めた話。
漁獲量が減ったり、カキが大きく育たない原因が海水にミネラルやリンを含む栄養素が減少したからだと考え、元をたどっていくと、森に行き着いた。
そして、長い年月をかけて人工林を整備し、植樹をした。
その結果、いままで以上に立派なカキが育つようになった。
そうなんです。
森をきれいにする事が、僕たちがいつもお世話になっている川の水をきれいにする事にする事にダイレクトに繋がるのです。

しかし、今、日本の森は健全な状態にはありません。
なぜでしょうか?
そして、Natural Actionスタッフが森にいる訳も。
次回に記事にしますね。
=================================
WE CONNECT YOU AND NATURE
自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する
NATURAL ACTION General Store
http://na-gs.jp/
=================================